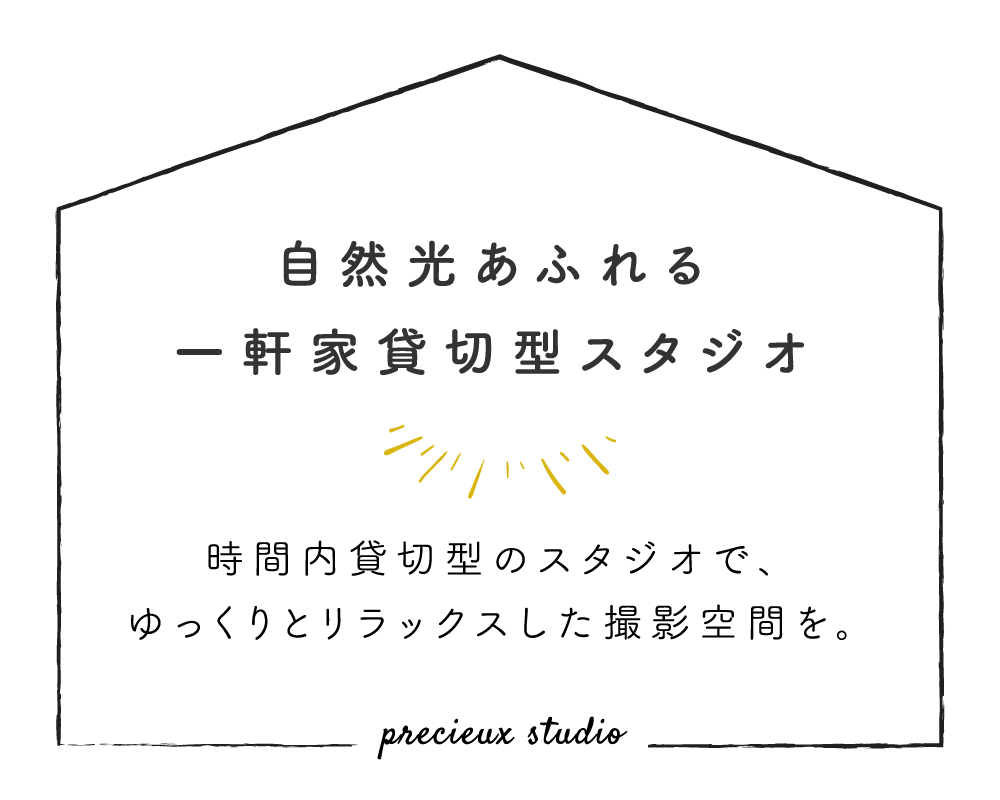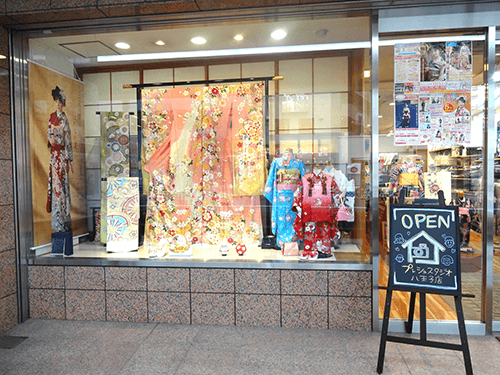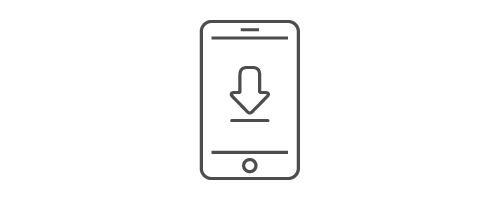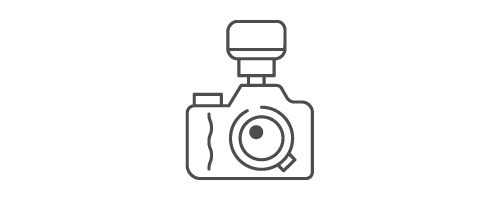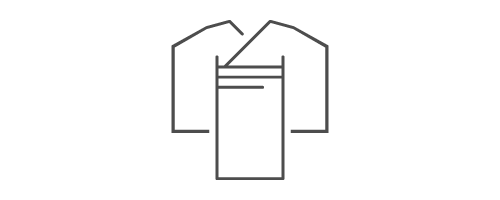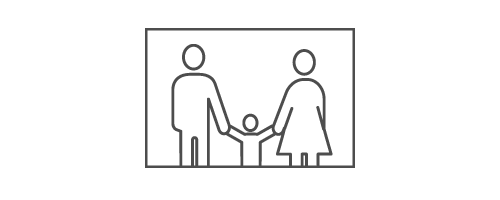記念撮影コラム Anniversary Photo Column
初宮参り(初宮詣)ってどんなお祝い?お宮参りの基礎知識

赤ちゃんが生まれてから最初に迎える大きな記念行事に初宮参り(はつみやまいり)があります。今回は、お宮参りとしても知られる初宮参り・初宮詣の基礎知識について一軒家貸切型写真館プレシュスタジオがまとめてご紹介します。
- 初宮参り・初宮詣はお宮参りの別名 神社で使われることが多い名称
- お寺ではお宮参りを初参りやお礼参りと呼ぶことも
- 生後1ヶ月以降に母子の健康第一で初宮参りのご祈祷を受ける
- どこの神社で初宮参りをするかは自由、お食い初めより前に祝うか同時に
- 初宮参りの赤ちゃんの祝い着・掛け着はレンタルもおすすめ
初宮参り・初宮詣とは?行事の意味や行く場所
お宮参りの別名、初宮参り・初宮詣で
赤ちゃんが誕生してからおよそ1ヶ月後に、近所の氏神様に初めてお参りすることを、初宮参り(はつみやまいり)、初宮詣(はつみやもうで)、お宮参り(おみやまいり)などと呼びます。初宮参りは赤ちゃんが無事に誕生したことの報告と感謝、および今後の健やかな成長を願って神社の神様にお参りするための行事で、日本では昔からの風習として多くの地域で行われています。
なお、お寺にお参りする場合は初参り(はつまいり)やお礼参り(おれいまいり)と呼びます。
現代の初宮参りで誰が赤ちゃんが抱っこするかは自由
かつては出産は汚れたものとして、産婦は不浄な身体として忌み明けまではさまざまな行動を制限されていた時代がありました。そういった背景や、産後でお母さんの体の負担が大きい時期であることから夫の母であるお姑さんが赤ちゃんを抱いて初宮参りを行っていました。
現代では家族揃って一緒に初宮参りをしますが、それでも伝統的に男性側の母が赤ちゃんを抱いてお参りする姿が多く見られます。しかし、今は両親と赤ちゃんだけでお参りするケースや、どちらか一方の祖父母が付き添うケースもあれば、両家や親族揃ってにぎやかに行うケースなどお参りの仕方も多様化しています。
あくまでも赤ちゃんとママの健康を第一に考えたいお祝い行事なので、ご家族にとって最適なタイミングや参加人数で初宮参りを計画しましょう。
お七夜・初宮参り・お食い初めなど赤ちゃんの記念行事は様々
初宮参りに限らず、赤ちゃんは生まれてから1歳を迎えるまでに実に数多くの儀式・記念行事がやってきます。
1歳までの赤ちゃんのお祝い・記念行事
- 【生後7日め】お七夜・命名式
- 【生後1ヶ月頃】お宮参り・初宮参り
- 【生後100日め】お食い初め・百日祝い
- 【生後6ヶ月】ハーフバースデー
- 【生後はじめての節句】初節句
- 【生後1年】ファーストバースデー・一升餅・選び取り
生後7日目にはお七夜、生後1ヶ月頃には初宮参り、100日目にはお食い初め、初節句、ファーストバースデーとなる1歳のお誕生日と、2歳以降に比べてとても記念日の多い1年になっています。
というのも、昔は今ほど医療技術や設備が整っておらず栄養価の豊富な食べ物が少なかったために、赤ちゃんが生を受けても生き永らえること自体が難しい時代がありました。そのため、たくさんの節目にお祝いの行事があり、その都度赤ちゃんの無事と健康を願ったのです。
こうして赤ちゃんの健康を祈願する行事が日本各地で祝い行事として少しずつ形を変え、今に至ります。
赤ちゃんの記念日は記念写真のベストタイミング
現代では生後1〜2週間から3週間までに撮る新生児撮影のニューボーンフォトや、ハーフバースデーとして赤ちゃんの生後6ヶ月をお祝いする行事もでき、新生児期よりも表情豊かになった赤ちゃんの可愛らしい姿を記念写真に残すご家族も多くなりました。
赤ちゃんも6ヶ月を迎える頃になると離乳食が始まったり、人見知りが出てきたり、日々成長を感じられる時期。
背中や腰が座る頃でもあり、うつぶせなどのポーズもできるようになって写真の撮り方にも幅が出てきます。ぜひ、可愛い写真をたくさん撮っておきましょう。
初宮参りはどこの神社に行くの?
初宮参りは、基本的には自宅近くの神社でその土地を守る神様にお参りするというのが習わしです。
昔は産院などがなく、お産婆さんを呼んで赤ちゃんを自宅出産することが主だったこともあり、産後のお母さんと赤ちゃんのために、移動が楽で体に負担のない近所の氏神様を祀る神社に出向いて氏子となることが一般的でした。
また、時代的な背景として女性が男性の家に嫁いで義父母と同居することがほとんどだったため、初宮参りには男性側の義母が付き添って、赤ちゃんを抱いて祈祷を受けるケースが多かったのです。
もちろん、自宅に戻ってから近くの神社に行っても、有名な大きめの神社に出向くのでも構いません。パパの地元や二人の思い出の土地、安産祈願をした神社でもどこでも、ママと赤ちゃんの体に負担にならない範囲のお出かけなら問題ありません。
いつまでに初宮参りに行くべき?

初宮参りは、男の子は生後30日か31日目、女の子は生後32日か33日目など地域により若干の違いがあり、中には50日目や100日目というところもあるようです。
厳密なルールなどはありません。
1ヶ月健診や母子の体調にあわせて神社にお参り
いつまでに初宮参りに行かなければならない、という決まりやマナーはないので、生後1ヶ月の1ヶ月健診を受けて外出が大丈夫そうなら、いつ行ってもいいのです。
一般的には家族の予定を合わせるために、1ヶ月健診の次の土日か、翌週の土日の間に行うことが多いかもしれません。
しかし、産後の母体の回復や天候によっては、日をずらしてもいいですし、家族それぞれの予定が合うなら週末よりも神社が空いている平日にお参りに行くのもおすすめです。過ごしやすい時間帯は季節によっても変わるので、以下のコラムも参考にしてみてください。
里帰り出産での初宮参りはどうする?
しかし、現代は里帰り出産をする家庭もあります。赤ちゃんの1ヶ月検診までは自宅に戻れない場合もあるでしょう。なかにはパパの実家が、自宅やママの実家から遠いご家庭では、赤ちゃんが生まれたときに駆けつけてもらっているなら、1ヶ月後に初宮参りでまた招待するのも気が引けるかもしれません。
そのような場合は、ママ側の親に付き添ってもらえば十分です。ママの地元の、ママが赤ちゃんのとき初宮参りをした神社と同じ神社にお参りするのも思い出深くて良いですね。
お食い初め・百日参りと初宮参りを兼ねる地域も
先ほどご紹介したように、初宮参りを行う時期は地域によって様々です。豪雪地帯の東北や北海道で真冬に生まれた赤ちゃんは、生後100日頃を目処に初宮参りを済ませる「百日参り(ももかまいり)」を行うこともあります。雪で足元が危なく寒さも厳しいため、無理してお参りする必要はありませんね。
一般的には百日祝いを行う時期になるので、お母さんの体調も安定しやすいメリットがあります。
初宮参りは昔からの習わしとはいえあまり堅苦しく考えず、ママと赤ちゃんの健康状態最優先で、都合の良い日に行くのが一番です。また、首の座らない赤ちゃんを抱いて傘をさすのは大変なので、雨天の心配がない日を選ぶのがおすすめです。
初宮参りの御祈祷の流れ
参拝の日取りと神社が決まったら、抑えておきたいのが初宮参りのご祈祷の流れです。
お参りは神社の受付所で、初宮参りの申込みと祈願料を納めます。
祈祷後に赤ちゃんの名入の記念品をもらえるところもありますので、申込みの際は赤ちゃんの名前をしっかりと正しく書きましょう(まれに、書き慣れていないため漢字を間違ってしまう親御さんもいるようですので注意しましょう)。
初穂料は神社への事前確認がおすすめ
初穂料は神社によってあらかじめ何段階かに定められている場合と、お気持ちで(いくらでも)という場合とさまざまなケースがあります。また、名称も初穂料の他に、祈願料や玉串料など神社により使い分けている場合があります。
事前に神社の公式サイトを確認しておくと、目安が掲載されていることもあるためアクセスや受付時間と一緒に確認しておくのがおすすめです。
初宮参りの御祈祷と記念品の受取
申込みを終えたら、案内があるまで待ちましょう。初詣の時期と重なると、厄除け祈願や商売繁盛祈願、合格祈願などの人が集まるためかなり時間がかかります。授乳は時間を見計らって済ませておくと安心ですね。
ご祈祷は、本殿や祈祷所で行われ、他の家族と一緒に神主さんに順番に赤ちゃんの名前を読み上げてもらいます。その後、玉串を捧げて拝礼して神主さんからお土産を受け取り退場します。神社の作法によって流れが異なる場合もありますが、祈祷のはじめに神主さんからの説明がありますので心配する必要はありません。
初宮参り・お宮参りはしなくてもいい?
初宮参りは体調や家族の都合を最優先
初宮参り・お宮参りは必ずしもお祝いしなければならない行事ではありません。
遠方から初宮参りのために両家の祖父母を招待するのが心苦しかったり、産後間もないママの身体の負担が大きい場合などは、無理をして初宮参りに出かける必要はないでしょう。
記念写真撮影で初宮参りをお祝い
体調面で安心して出かけられる時期が来たら、そのときに初宮参りを行えば良いですし、形として記念をきちんと残したいなら、写真館で初宮参りの記念撮影をするのもおすすめです。
お宮参りの撮影におすすめの時期は、生後2,3ヶ月頃です。この頃になると、あやすと反応を見せてくれるようになり、表情豊かな写真をとることができます。
撮影の予約の時間帯も重要なポイントです。いつもお昼寝をしている時間は避けましょう。
また撮影前の授乳の時間を調整したり、赤ちゃんのコンディションがいい時間帯に予約をすることをおすすめします。
子育ては予定通りに行かないことが多いもの。なかでも、赤ちゃんの時期はあっという間に過ぎてしまいます。だからこそ、そのときどきの思い出を家族と一緒に写真館で撮影して記録するのはかけがえのない体験になります。写真館ならお宮参り用の掛け着・祝い着など着物もレンタルできますので、貸衣装店でレンタルするよりもリーズナブルでお得です。
お参り時にお宮参り用の掛け着レンタルサービスを行なっている写真館もありますので、全部お任せできるのはありがたいですね。
また写真館で撮影する際には撮影時にのみマスクを外したり、消毒しながら進められるので安心もあり、また手伝ってくれる人の手も多いことからママの体の負担も少なくなることと思います。
安全面の不安は事前確認を 感染症対策のおすすめ写真館
特に、2020年以降は新型コロナウイルス感染症対策のため、神社でも初宮参りに関してさまざまな安全対策が取られています。
マスクの着用、手洗い励行、手指の消毒、検温などを行い、完全予約制で少人数制で執行したり、参加者全員の氏名や連絡先の記入を義務化したりなどで対応しているところもあり、神社の方針によってさまざまな感染予防策が取られています。
ご家族の安心安全のために、出かける際は事前に神社の公式サイトなどで確認のうえ出かけることをおすすめします。
こども写真館プレシュスタジオ貸切型写真撮影
あわせて読みたい赤ちゃんの記念行事コラム
おすすめの記念撮影コラム
- 七五三(753)
- お宮参り・初宮参り・初宮詣
- 誕生日のバースデーフォト
- 赤ちゃんの記念行事
- 新生児ニューボーンフォト
- 家族写真 記念撮影
- 入園入学・卒園卒業記念
- 卒業袴・1/2成人式・十三参り
- 成人式写真 20歳の振袖写真
- マタニティフォト
- フォトウェディング
- 写真館の選び方
- 写真の撮り方ガイド
- #ママ向け
- #写真
- #七五三
- #女の子のお祝い
- #男の子のお祝い
- #衣装 #服装
- #マナー
- #0歳~1歳の赤ちゃん
- #いつ #時期
- #写真館 #スタジオ
- #お参り
- #神社 #寺社
- #家族
- #着物
- #3歳
- #セルフ
- #5歳
- #7歳
- #ご祈祷の初穂料
- #東京都
- #費用
- #レンタル #貸衣装
- #由来
- #前撮り
- #ギフト #プレゼント
- #祖父母
- #髪型
- #神奈川県
- 七五三はいつ?満年齢?数え年?お祝いと写真撮影のおすすめ時期
- お宮参りの服装は何を着る?赤ちゃんと両親の着物や髪型をおさえよう
- 1歳までの赤ちゃんのお祝いイベントカレンダー お食い初め 100日祝い等
- お祝い袋・ご祝儀袋の書き方をマスター!表書きや封筒・中袋・入れ方も 七五三やお宮参り・結婚式に
- 孫のお宮参り!祖父母は何をするの?祝い金は皆どうしてる?
- 赤ちゃんの泣き相撲とは?健康祈願の記念行事の由来と開催神社情報
- 男の子の七五三で鎧兜・甲冑撮影ってどう?メリットデメリットと写真館別プランを比較解説
- 居木神社に七五三&お宮参り!泣き相撲も有名な東京都品川区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報
- 3歳の七五三に人気の和装!写真で見るレンタル着物・被布・羽織袴コーデ
- 東京五社にお参り!七五三・お宮参りにおすすめの神社アクセス&ご祈祷初穂料
- はじめての七五三着物レンタルガイド 3歳の七五三に人気の衣装をレンタルするには?
- 大國魂神社に七五三&お宮参り!厄除けで人気の東京都府中市の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報
- 家族でレンタル着物を借りるなら下着・インナーの正しい知識もおさえよう
- 池上本門寺に七五三&お宮参り!お会式が有名な東京都大田区のお寺のご祈祷料・写真撮影情報
- お宮参りは両家トラブルに注意!参加者・誰が抱っこするかを話し合おう
- 子安神社に七五三&お宮参り!安産祈願で人気の東京都八王子の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報
- 子供のレンタル着物を借りる前に!クリーニング・着付け・キャンセル・左前等貸着物の知識
- 西新井大師に七五三&お宮参り!東京都足立区の總持寺=関東の高野山のお寺参りの流れやご祈祷料・写真撮影情報
- 七五三の着付けは美容院で頼めない?レンタル着物の意外な落とし穴
- 東京大神宮に七五三&お宮参り!東京の伊勢神宮にあたる飯田橋の神社のご祈祷初穂料・写真撮影情報
おすすめ記念行事コラムRecommended Column

赤ちゃんの泣き相撲とは?健康祈願の記念行事の由来と開催神社情報

男の子の七五三で鎧兜・甲冑撮影ってどう?メリットデメリットと写真館別プランを比較解説

居木神社に七五三&お宮参り!泣き相撲も有名な東京都品川区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

3歳の七五三に人気の和装!写真で見るレンタル着物・被布・羽織袴コーデ

東京五社にお参り!七五三・お宮参りにおすすめの神社アクセス&ご祈祷初穂料

はじめての七五三着物レンタルガイド 3歳の七五三に人気の衣装をレンタルするには?

大國魂神社に七五三&お宮参り!厄除けで人気の東京都府中市の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

家族でレンタル着物を借りるなら下着・インナーの正しい知識もおさえよう

池上本門寺に七五三&お宮参り!お会式が有名な東京都大田区のお寺のご祈祷料・写真撮影情報

お宮参りは両家トラブルに注意!参加者・誰が抱っこするかを話し合おう

子安神社に七五三&お宮参り!安産祈願で人気の東京都八王子の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

子供のレンタル着物を借りる前に!クリーニング・着付け・キャンセル・左前等貸着物の知識

西新井大師に七五三&お宮参り!東京都足立区の總持寺=関東の高野山のお寺参りの流れやご祈祷料・写真撮影情報

七五三の着付けは美容院で頼めない?レンタル着物の意外な落とし穴

東京大神宮に七五三&お宮参り!東京の伊勢神宮にあたる飯田橋の神社のご祈祷初穂料・写真撮影情報

お宮参りはいつまでに祝うべき?写真撮影&お参りは生後6ヶ月までがおすすめの理由

お祝い袋・ご祝儀袋の書き方をマスター!表書きや封筒・中袋・入れ方も 七五三やお宮参り・結婚式に

七五三はいつ?満年齢?数え年?お祝いと写真撮影のおすすめ時期

1歳までの赤ちゃんのお祝いイベントカレンダー お食い初め 100日祝い等

お宮参りの服装は何を着る?赤ちゃんと両親の着物や髪型をおさえよう

玉串料はいつ必要?初穂料との違いと相場・書き方・お札の向きを解説

生後3ヶ月の赤ちゃんはどんな時期?成長(体重・睡眠・できること)の変化&お食い初め写真・ベビーフォト撮影のポイント

お宮参りでおでこに文字を書く地域は関西だけ?点・大・小等額の印としきたりの意味 関東は書かない?

早生まれの子供の七五三はいつ祝う?数え年と満年齢それぞれのベストなタイミングを解説

孫のお宮参り!祖父母は何をするの?祝い金は皆どうしてる?

夏のお宮参りは何を着る?お参り当日の衣装と時間帯のポイント

写真を印刷するならどのサイズ?意外と知らない写真の大きさ一覧

生後半年のハーフバースデーは何をする?お祝い写真や飾り・離乳食ケーキ

安産祈願はいつ?戌の日参り・帯祝いにおすすめの東京の安産祈願神社・寺社 マタニティフォトの前に母子健康を祈ろう

写真撮影を贈り物に!出産祝いやお誕生日祝いにもおすすめのフォトギフトカードの選び方

お宮参り当日の持ち物リスト 初穂料・封筒・小物等必要なものを準備しよう

生後6ヶ月の赤ちゃんはどんな時期?成長・発育と生後半年のハーフバースデー写真撮影のポイント

男の子の七五三で鎧兜・甲冑撮影ってどう?メリットデメリットと写真館別プランを比較解説

居木神社に七五三&お宮参り!泣き相撲も有名な東京都品川区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

3歳の七五三に人気の和装!写真で見るレンタル着物・被布・羽織袴コーデ

東京五社にお参り!七五三・お宮参りにおすすめの神社アクセス&ご祈祷初穂料

はじめての七五三着物レンタルガイド 3歳の七五三に人気の衣装をレンタルするには?

大國魂神社に七五三&お宮参り!厄除けで人気の東京都府中市の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

家族でレンタル着物を借りるなら下着・インナーの正しい知識もおさえよう

池上本門寺に七五三&お宮参り!お会式が有名な東京都大田区のお寺のご祈祷料・写真撮影情報

子安神社に七五三&お宮参り!安産祈願で人気の東京都八王子の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

子供のレンタル着物を借りる前に!クリーニング・着付け・キャンセル・左前等貸着物の知識

西新井大師に七五三&お宮参り!東京都足立区の總持寺=関東の高野山のお寺参りの流れやご祈祷料・写真撮影情報

七五三の着付けは美容院で頼めない?レンタル着物の意外な落とし穴

東京大神宮に七五三&お宮参り!東京の伊勢神宮にあたる飯田橋の神社のご祈祷初穂料・写真撮影情報

亀戸天神社に七五三&お宮参り!東京都江東区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

七五三のお祝いは人それぞれ!いつ何をするか計画しよう スケジュール例紹介

住吉神社に七五三&お宮参り!東京都中央区佃の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

お祝い袋・ご祝儀袋の書き方をマスター!表書きや封筒・中袋・入れ方も 七五三やお宮参り・結婚式に

七五三はいつ?満年齢?数え年?お祝いと写真撮影のおすすめ時期

玉串料はいつ必要?初穂料との違いと相場・書き方・お札の向きを解説

早生まれの子供の七五三はいつ祝う?数え年と満年齢それぞれのベストなタイミングを解説

データのみ写真館は手軽で安い!七五三におすすめのおしゃれなフォトスタジオ

3歳の七五三に!女の子に人気の髪型・簡単ヘアアレンジ紹介

七五三の食事会・お祝いのご飯会は必要?祝い膳メニュー&おすすめランチ

寒川神社へ七五三参り!お参りの流れや八方除け・ご祈祷の初穂料・写真撮影情報(神奈川県)

鶴岡八幡宮へ七五三参り!神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・神奈川県鎌倉市の写真撮影情報

七五三のヘアセットは美容院?自宅?着付けや希望の髪型で選ぶ3歳・5歳・7歳ヘアメイクガイド

亀戸天神社に七五三&お宮参り!東京都江東区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

七五三写真撮影で付き添いの兄弟・姉妹の服装はどうすべき?

神社は写真撮影禁止?七五三やお宮参りの神社撮影のマナーとポイント

七五三は明治神宮(東京都渋谷区)にお参り!神社参拝の流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

七五三の靴選び 3歳は草履・下駄以外にスニーカーでもOK?

七五三ママの髪型 訪問着・和装&洋装に合うヘアアレンジを長さ別に紹介

居木神社に七五三&お宮参り!泣き相撲も有名な東京都品川区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

東京五社にお参り!七五三・お宮参りにおすすめの神社アクセス&ご祈祷初穂料

大國魂神社に七五三&お宮参り!厄除けで人気の東京都府中市の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

池上本門寺に七五三&お宮参り!お会式が有名な東京都大田区のお寺のご祈祷料・写真撮影情報

お宮参りは両家トラブルに注意!参加者・誰が抱っこするかを話し合おう

子安神社に七五三&お宮参り!安産祈願で人気の東京都八王子の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

子供のレンタル着物を借りる前に!クリーニング・着付け・キャンセル・左前等貸着物の知識

西新井大師に七五三&お宮参り!東京都足立区の總持寺=関東の高野山のお寺参りの流れやご祈祷料・写真撮影情報

東京大神宮に七五三&お宮参り!東京の伊勢神宮にあたる飯田橋の神社のご祈祷初穂料・写真撮影情報

お宮参りはいつまでに祝うべき?写真撮影&お参りは生後6ヶ月までがおすすめの理由

亀戸天神社に七五三&お宮参り!東京都江東区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

住吉神社に七五三&お宮参り!東京都中央区佃の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

桜神宮に七五三&お宮参り!東京都世田谷区桜新町の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

代々木八幡宮に七五三&お宮参り!東京都渋谷区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

松陰神社に七五三&お宮参り!東京都世田谷区で吉田松陰ゆかりの神社お参り・ご祈祷の流れや写真撮影情報

冬のお宮参りに!赤ちゃん・ママ・祖母の服装と日程選び/お参りのポイント

お祝い袋・ご祝儀袋の書き方をマスター!表書きや封筒・中袋・入れ方も 七五三やお宮参り・結婚式に

1歳までの赤ちゃんのお祝いイベントカレンダー お食い初め 100日祝い等

お宮参りの服装は何を着る?赤ちゃんと両親の着物や髪型をおさえよう

玉串料はいつ必要?初穂料との違いと相場・書き方・お札の向きを解説

お宮参りでおでこに文字を書く地域は関西だけ?点・大・小等額の印としきたりの意味 関東は書かない?

孫のお宮参り!祖父母は何をするの?祝い金は皆どうしてる?

夏のお宮参りは何を着る?お参り当日の衣装と時間帯のポイント

写真撮影を贈り物に!出産祝いやお誕生日祝いにもおすすめのフォトギフトカードの選び方

お宮参り当日の持ち物リスト 初穂料・封筒・小物等必要なものを準備しよう

お宮参りに必要なお金はいくら?誰が出す?気になる費用&相場を知ろう

お宮参りでパパの服装・スーツのポイントは?ネクタイは何色がいい?

お宮参りは両家トラブルに注意!参加者・誰が抱っこするかを話し合おう

初宮参り(初宮詣)ってどんなお祝い?お宮参りの基礎知識

東京&神奈川のお宮参り おすすめ神社・寺8選と初穂料の目安を紹介

亀戸天神社に七五三&お宮参り!東京都江東区の神社お参りの流れやご祈祷の初穂料・写真撮影情報

お宮参りのお祝いの封筒をぶら下げる紐銭・帯銭とは?大阪・関西の風習 産土参りの費用相場と地域文化

お食い初めは写真撮影も思い出に!百日祝いにおすすめのスタジオ特集

犬と撮れる写真館!ペットフォトスタジオの選び方&東京都内おすすめ3選

二分の一成人式で写真を撮るなら自分らしく!ハーフ成人式の衣装&撮影内容

無料のマタニティフォトはここに注意!後悔しないスタジオ選びのポイントはデータ&プライバシー

マタニティフォトはどんなポーズが人気?おしゃれ~夫婦・家族で撮る面白系までおすすめポーズ集

おしゃれな七五三アルバム・フォトブックの作り方&上手な753写真選び

夫婦でマタニティフォト!旦那さんと2人で撮る安産祈願写真のポーズ&アイデア

マタニティフォト撮影はプライベート空間が重要!100名アンケート調査結果公開

1歳のお誕生日写真にもおすすめ!ファーストシューズの選び方

マタニティフォトを花束やシールで華やかに!ペイントなしでもおしゃれな写真になる演出・グッズ

母子手帳&エコー写真を上手に活用!マタニティフォトにおすすめの小物・小道具

1歳のお誕生日に!赤ちゃんが手づかみで食べるスマッシュケーキにはどんな効果がある?

ベビーフォトスタジオに学ぶ!写真撮影で赤ちゃんを泣き止ませるコツはある?

お宮参りに必要なお金はいくら?誰が出す?気になる費用&相場を知ろう

お宮参りはスタジオ着物レンタルが便利!200名アンケート調査結果公開

こども写真館比較サイト・ランキングの上手な見方 スタジオ選び活用方法